熊の出没が連日ニュースになり、「猟友会」「猟銃」などを耳にする機会が増えています。
本記事は、「猟師ってどうやって始めるの?」という関心を持った方向けに、狩猟免許の種類と取得の流れ、銃の所持許可、猟友会について、まず知っておくべき基礎をまとめました。
狩猟免許の取得は、野生動物や、日本における狩猟のための法律の知識を得る意味でも非常にためになります。
狩猟免許を取得しても狩猟ができるようになるためには別の手続きが必要になりますが、全体感を知り、野生動物との付き合い方を学びましょう。
狩猟免許の種類(4区分)と年齢要件
- 第一種銃猟免許:装薬銃(散弾銃・ライフル銃)と空気銃が対象
- 第二種銃猟免許:空気銃のみ
- わな猟免許:箱わな、くくりわな等
- 網猟免許:はり網、むそう網 等
年齢要件の目安:銃猟免許は20歳以上、わな・網は18歳以上が原則です(都道府県が実施する狩猟免許試験の欠格事由に基づく)。銃で狩猟するには、免許のほかに警察の「銃砲所持許可」が別途必要です。
狩猟免許の取得フロー(都道府県実施)
- 事前講習(任意):各地の猟友会や自治体が実施。法令や安全、鳥獣判別、猟具の基礎などを学ぶ。場所にもよるが、基本的に試験に出るところを教えてくれるので時間が許すのであれば参加すると安心。YouTubeなどの動画よりも確実にその都道府県にあった問題を教えてくれる。
実際に私は講習に行き、前日に復習する程度で取得できた。
私の時は本当に講習で指摘があった問題が出てきた(その年・地域による)。また、狩猟鳥獣か非狩猟鳥獣か判別する試験も、実際の試験で使われる画像を講習会でも使われており、非常に有用であった。 - 申請:住所地の都道府県へ受験申請。顔写真、身分証、診断書等が必要(自治体で差)。
- 試験:適性(視力・聴力・運動)/学科(法令・安全)/実技。
実技は、銃の模擬操作や猟具の取り扱い、鳥獣判別・距離目測 等。おおよそ1日で終わる。 - 免許交付:合格すると都道府県知事名で免許状が交付。
スケジュール感:試験は毎年複数回。狩猟期(例:秋〜冬)前の夏〜秋に集中しがちです。受験日・会場・手数料は都道府県の告知を確認しましょう。
基本的に猟期が10月〜11月からなので、それまでに免許の交付を受けられるように取得するのをお勧めします。
地域によっては有害鳥獣駆除を担えますが、そのためには前年度の狩猟登録が必須になるので、スケジュールややりたいことを考えながら早めに準備しましょう。
難易度:都道府県によって多少難易度に差があるという噂も聞きます。
猟師として活動するには活動する地域での登録が必要ですが、免許自体は全国で利用可能です。移住して狩猟を行いたいと考えている人は、事前にその地域の人に狩猟免許取得について聞いてみるのをお勧めします。
銃を使う人は「銃砲所持許可」が別途必要
銃(散弾銃・ライフル銃・空気銃)を所持するには、住所地の警察(公安委員会)での許可が必要です。初心者はまず講習と適性手続を経て、許可後に銃を購入します(ライフル銃は一定の経験・条件が必要)。保管は金庫・装薬庫などの基準を満たさなければなりません。
- 講習:猟銃等講習会(初心者講習・考査)→合格
- 申請:診断書、経歴書、同居親族書、住民票等/身辺調査・自宅訪問
- 教習射撃:射撃場での実技(初心者は教習資格認定後)
- 保管設備:銃砲保管庫・装薬保管庫の設置
年齢の目安:所持許可は原則20歳以上(競技等の特例を除く)。欠格事由(一定の病気・薬物中毒・犯罪歴 等)に該当する場合は許可されません。詳細は最寄りの警察署・生活安全課へ問い合わせ。
銃の免許は比較的簡単に取得できますが、銃の所持許可を取るハードルが高いです。
また、基本的には散弾銃を10年間所持し適切に管理していると、ライフル銃を所持・使用できるようになります。
猟友会とは?(入会は任意/メリット多数)
- 地域のハンター団体:都道府県猟友会〜大日本猟友会のネットワーク。入会は任意で、狩猟を趣味で行う人たちの集まりと捉えておくと良い。
- 学べる:事前講習、安全教育、鳥獣判別、地域の狩場の慣習やマナー、ジビエの調理など定期的に講習が開催される。
- つながる:新人が先輩に同行して現場を見られる機会
- サポート:狩猟者登録の手続きや保険手配の案内、有害鳥獣対策協力 等。
初めての方は、わな猟免許から始めて現場の安全や法令運用に慣れつつ、必要に応じて銃の所持許可を目指すルートも一般的です。地域の猟友会に相談すると具体的なステップが見えやすくなります。
地方では自治体職員が猟友会の事務を行なっている場合もあり、よほどの理由がない限りは参加しておくのをおすすめします。
よくある質問
Q. 費用はどのくらい?
A. 受験料・手数料・講習費等で数万円規模(自治体差)。さらに免許取得後は登録・狩猟税・保険などでさらに数万円、罠が一つ数千円。さらに銃を持つ場合は、講習・保管庫・射撃場費用・銃本体でさらに数十万円〜の初期投資を想定しましょう。
私の時は、事前講習で8千円、免許試験や狩猟登録、狩猟税で2万円程度、それと保険代、毎年登録の際に1.5万円程度かかっています。
Q. いつ受けるのが良い?
A. 多くの都道府県は夏〜秋に試験を集中実施。早めに準備し、事前講習で実技(安全操作・鳥獣判別・距離目測)に慣れておくと安心です。
野生動物を獲ることでもらえる報奨金について👉熊を倒すと○万円?!野生動物を駆除した時の報奨金額: 有害鳥獣駆除を担う人・手続き・補助金(報償金)の基礎知識
次の一歩
- 免許を取る
- 銃を持つ人は所持許可を取る(警察手続)
- 狩猟者登録(毎シーズン・都道府県ごと)
- 保険加入:対人・対物3,000万円以上(狩猟者登録の要件)
- 安全と地域ルール:地図・ハンターマップ確認、立入禁止・保護区・住宅地近接の安全距離 など
まとめ:狩猟は法令・安全・地域の知恵を総合して行う活動です。まずは免許の種類・警察手続・猟友会の役割を押さえ、事前講習で安全第一の基礎を固めましょう。

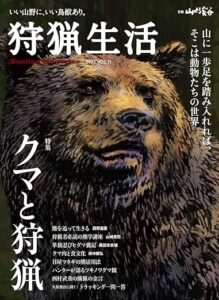
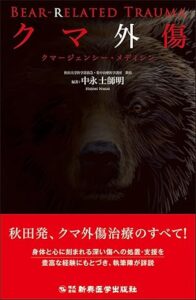


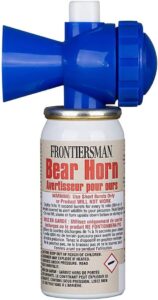
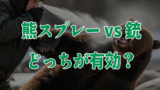
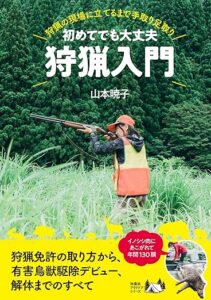
-120x68.jpeg)
-120x68.jpeg)
コメント